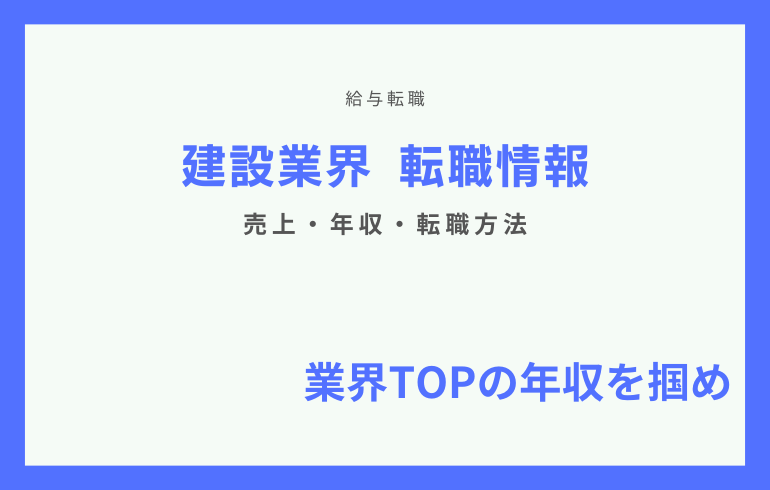建設業界は日本経済の基盤を支える重要な産業であり、特にゼネコン業界は大規模なプロジェクトを手掛けることで知られています。2024年現在、ゼネコン各社の給与水準はどのように変化しているのでしょうか?本記事では、高年収ランキングをもとに各社の給与が高い理由やその背景にある業界動向を解説します。就職・転職を考える方にとっても、知っておくべき最新情報をお届けします。
目次
【スーパーゼネコン】年収ランキング
スーパーゼネコンと呼ばれる建設業界を引っ張っている企業の平均年収をランキング形式で表すと以下のようになります。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1位 | 鹿島建設 | 1,163万円 |
| 2位 | 大林組 | 1,031万円 |
| 3位 | 竹中工務店 | 1,012万円 |
| 4位 | 大成建設 | 992万円 |
| 5位 | 清水建設 | 971万円 |
1位:鹿島建設(平均年収:1,163万円)

引用:鹿島建設
鹿島建設は、日本を代表するスーパーゼネコンであり、国内外で幅広い事業を展開しています。主な事業には、トンネルや橋梁などのインフラ施設を手掛ける土木事業、建築事業、エンジニアリング事業、国内外の不動産開発事業があります。特に、北米、アジア、欧州、大洋州での建築・設計活動が顕著です。さらに、エンジニアリング事業では医薬品や食品分野、環境事業では新エネルギーや土壌汚染対策なども手掛けています。連結売上高は2兆円を超え、国内トップクラスの売上を誇ります。本社は東京都港区元赤坂にあり、現代表取締役会長は押味至一氏です。
| 会社名 | 鹿島建設株式会社 |
| 売上 | 2,391億円 |
| 社員数 | 8,129人 |
| 平均年収 | 1,163.5万円 |
| 初任給 | |
| 平均残業 | – |
| 有給取得 | – |
| 平均年齢 | 43.9歳 |
2位:大林組(平均年収:1,031万円)

引用:大林組
大林組は、国内外で土木・建築事業を展開する日本を代表するスーパーゼネコンです。国内ではオフィス、マンション、商業施設、工場、病院、学校など多様な建築物を提供し、トンネル、橋梁、ダム、河川、鉄道や高速道路などのインフラ建設にも注力しています。海外では東南アジア、北米、オセアニアを中心に事業を展開し、地域社会に貢献しています。さらに、都心部での優良賃貸不動産開発や再生可能エネルギー事業、PPP・コンセッションなど新領域ビジネスにも取り組んでいます。本社は東京都港区に位置しています。
| 会社名 | 株式会社大林組 |
| 売上 | 1兆9,838億円 |
| 社員数 | 9,134人 |
| 平均年収 | 1,031.5万円 |
| 初任給 | |
| 平均残業 | – |
| 有給取得 | – |
| 平均年齢 | 42.7歳 |
3位:竹中工務店(平均年収:1,012万円)

引用:竹中工務店
竹中工務店は、日本を代表するスーパーゼネコンで、国内外で土木事業や建築事業を展開しています。売上高は国内トップクラスで、連結売上高は1兆3,000億円を超えています。主要事業として、建築工事、土木工事、道路舗装、海外建設、事務所ビル賃貸、リゾート開発などがあります。本社は大阪市中央区本町に位置し、国内外で多岐にわたるプロジェクトを手掛けています。
| 会社名 | 株式会社竹中工務店 |
| 売上 | 1,612億円 |
| 社員数 | 7,786人 |
| 平均年収 | 1,012.8万円 |
| 初任給 | |
| 平均残業 | – |
| 有給取得 | – |
| 平均年齢 | 44.6歳 |
4位:大成建設(平均年収:992万円)

引用:大成建設
大成建設は、日本を代表するスーパーゼネコンであり、国内外で建築・土木、環境、エンジニアリング、原子力、都市開発、不動産など多岐にわたる事業を展開しています。連結売上高は1.6兆円を超え、国内トップクラスの実績を誇ります。主要な事業は、国内建築(8,994億円)、国内土木(4,020億円)、海外建設(776億円)、開発事業(1,329億円)、エンジニアリング(275億円)です。現代表取締役社長は相川善郎氏で、本社は東京新宿区に位置しています。
| 会社名 | 大成建設株式会社 |
| 売上 | 1,642億円 |
| 社員数 | 8,163人 |
| 平均年収 | 992.9万円 |
| 初任給 | |
| 平均残業 | – |
| 有給取得 | – |
| 平均年齢 | 43.0歳 |
5位:清水建設(平均年収:971万円)

引用:清水建設
清水建設は、国内外で土木・建築事業を展開する日本を代表するスーパーゼネコンです。国内トップクラスの売上高を誇り、連結売上高は約2兆円に達します。建築事業ではオフィスや病院などの設計・施工・維持管理を行い、土木事業ではトンネルや橋梁などのインフラ整備を手掛けます。海外では南アジアを中心に、超高層ビルや地下鉄などを建設しています。さらに、不動産開発やエンジニアリング事業も展開し、エネルギーや環境浄化分野にも注力しています。本社は東京都中央区京橋にあり、井上和幸氏が代表取締役会長を務めています。
| 会社名 | 清水建設株式会社 |
| 売上 | 1兆9,338億円 |
| 社員数 | 10,845人 |
| 平均年収 | 971.6万円 |
| 初任給 | |
| 平均残業 | – |
| 有給取得 | – |
| 平均年齢 | 43.4歳 |
ゼネコン業界のビジネスモデル: 建設業界の中核を担う総合力

ゼネコン(ゼネラル・コントラクター)は、建設業界の中心的存在として多岐にわたるプロジェクトを管理・遂行する企業です。そのビジネスモデルは、単なる建設作業の請負に留まらず、企画・設計から施工、さらには維持管理までを一貫して提供する総合力にあります。ゼネコンの活動は、公共事業から民間プロジェクト、大規模インフラ整備から住宅建設まで多岐にわたり、社会の基盤を支える重要な役割を果たしています。
総合的なプロジェクト管理
ゼネコンのビジネスモデルの核となるのが、プロジェクトのトータルマネジメントです。これは、プロジェクトの初期段階である企画・設計から、実際の施工、さらには完成後の維持管理までを包括的にカバーするものです。プロジェクトの全体像を把握し、各工程がスムーズに進行するように管理することで、高品質な成果物を提供します。
- 企画・設計: ゼネコンは、プロジェクトのコンセプト設計や詳細設計を行います。この段階では、建築家やエンジニアと協力しながら、クライアントの要求を具体化し、実現可能なプランを作成します。
- 施工管理: 実際の建設作業を取り仕切る施工管理は、ゼネコンの中心的な役割です。現場では、安全管理、品質管理、スケジュール管理、コスト管理などが厳密に行われ、計画通りにプロジェクトが進行するように調整します。
- 維持管理: 完成後の建物やインフラの維持管理もゼネコンの重要な業務です。定期的な点検や修繕、リニューアルなどを行い、長期的な視点でプロジェクトの価値を維持・向上させます。
多岐にわたるサービス提供
ゼネコンのビジネスモデルは、多様なサービスの提供を通じて収益を上げる仕組みになっています。以下に、主要なサービス分野を紹介します。
- 建築工事: 住宅、オフィスビル、商業施設、公共施設など、多種多様な建築物を手掛けます。最新の建築技術とデザインを取り入れ、クライアントの要望に応じたカスタマイズを行います。
- 土木工事: 道路、橋梁、トンネル、ダムなど、大規模なインフラプロジェクトを担当します。土木工事は、社会の基盤を支える重要な役割を担っており、高度な技術力と経験が求められます。
- リニューアル工事: 既存の建物やインフラの改修・修繕を行います。耐震補強やエネルギー効率の向上など、現代のニーズに合わせたリニューアルを提案し、実施します。
- PPP/PFI事業: 公共事業を民間の資金とノウハウで運営するPPP(Public Private Partnership)やPFI(Private Finance Initiative)事業にも積極的に取り組んでいます。これにより、公共サービスの質を向上させるとともに、新たな収益源を確保しています。
グローバルな展開と競争力
ゼネコンは国内だけでなく、海外市場にも積極的に進出しています。特に新興国ではインフラ整備の需要が高く、日本のゼネコンはその高い技術力と信頼性を武器に、数多くのプロジェクトを手掛けています。グローバルな視点でビジネスを展開することで、成長市場におけるビジネスチャンスを捉え、収益基盤を強化しています。
高度な技術力とイノベーション
ゼネコンは、常に最新の建設技術を追求し、イノベーションを取り入れることで競争力を維持しています。建設現場でのIT技術の活用、環境に配慮したエコ建材の導入、労働生産性の向上を図るロボティクスの活用など、様々な分野で技術革新を進めています。これにより、クライアントに対して高付加価値なサービスを提供し、市場での優位性を確保しています。
持続可能な社会への貢献
ゼネコンは、持続可能な社会の実現に向けた取り組みにも力を入れています。環境負荷の低減やエネルギー効率の向上、地域社会との共生を目指し、持続可能な開発目標(SDGs)に基づいたプロジェクトを推進しています。これにより、社会的責任を果たしながら、企業としての信頼性とブランド価値を高めています。
ゼネコンの売上規模に呼ばれ方の違い

| スーパーゼネコン | 売上高が1兆円を超えている |
| 準大手ゼネコン | 売上高が3,000億円程度(明確な定義はない) |
| 中堅ゼネコン | 売上高が1,000億円程度(明確な定義はない) |
スーパーゼネコン
スーパーゼネコン(大手ゼネコン)は、企業としての売上が1兆円以上であり、従業員数も5,000人以上の企業を指します。また、工事内容を建築と土木で分けた場合、圧倒的に建築の方が比率が高い(7割から8割程度が多い)点も特徴です。
スーパーゼネコン(大手ゼネコン)に該当するのは次の企業です。
| 清水建設 | |||
| 鹿島建設 | |||
| 大林組 | |||
| 大成建設 | |||
| 竹中工務店 |
準大手ゼネコン
企業としての売上が3,000億円程度で、従業員数は2,000から6,000人未満となっているケースが多くなっています。準大手ゼネコンに該当する企業は次のとおりです。
| 長谷工コーポレーション | |||
| フジタ | |||
| 五洋建設 | |||
| 戸田建設 | |||
| 前田建設工業 | |||
| 安藤ハザマ | |||
| 三井住友建設 | |||
| 西松建設 | |||
| 熊谷組 | |||
| 東急建設 |
中堅ゼネコン
中堅ゼネコンは売上高が1,000億円ほどで、従業員数は900から3,000人程度となっています。独自の技術や工法を保有しており、小中規模のプロジェクトを実施するケースが多い点が特徴です。
次の企業が中堅ゼネコンに該当します。
| 奥村組 | |||
| 東亜建設工業 | |||
| 鉄建建設 | |||
| 東洋建設 | |||
| 淺沼組 | |||
| 大豊建設 | |||
| 飛島建設 | |||
| 銭高組 | |||
| 鴻池組 | |||
| 東鉄工業 | |||
| 福田組 |
ゼネコン業界が高年収と呼ばれる理由

ゼネコン業界が高年収と呼ばれる理由は、いくつかの重要な要因によって説明できます。この章では、その主要な理由について詳しく見ていきます。
専門性の高さと技術力の要求
ゼネコン(総合建設業者)業界は、高度な専門知識と技術力が必要とされる分野です。建設プロジェクトは、設計、施工、管理、品質保証など多岐にわたる業務を含みます。これには、建築学、土木工学、機械工学、電気工学など、さまざまな専門知識が求められます。また、大規模なプロジェクトの成功には、優れた技術力と経験が不可欠です。こうした専門性と技術力を持つ人材は、需要が高く、相応の報酬が支払われる傾向にあります。
プロジェクトの規模と責任の重さ
ゼネコンが手掛けるプロジェクトは、しばしば数十億円から数百億円に及ぶ大規模なものです。これには商業ビル、公共インフラ、住宅地開発などが含まれます。大規模プロジェクトでは、予算管理、スケジュール管理、安全管理など、多くの責任が伴います。プロジェクトマネージャーや現場監督は、このような大規模プロジェクトを成功に導くために重要な役割を果たします。その責任の重さに応じて、高い報酬が提供されるのです。
高いリスクと複雑な調整
建設業界は、リスク管理が非常に重要です。天候、資材の供給問題、法的規制、労働力不足など、多くのリスク要因があります。ゼネコンは、これらのリスクを管理し、プロジェクトが順調に進行するようにしなければなりません。また、多くのステークホルダー(顧客、サブコン、政府機関、地域住民など)との調整が必要です。このような複雑な調整業務も高いスキルと経験を要し、その対価として高い給与が支払われます。
高収益性の事業構造
ゼネコン業界は、一般的に高収益性の事業構造を持っています。特に、大規模プロジェクトや公共インフラプロジェクトは、長期的な収益を見込める案件が多いです。これらのプロジェクトは、安定したキャッシュフローを生み出し、企業全体の収益を高めます。その結果、企業は優秀な人材を引き付け、維持するために高い給与を提供することができるのです。
経験とスキルの蓄積による報酬の上昇
ゼネコン業界では、経験とスキルの蓄積が重要視されます。経験豊富なエンジニアやマネージャーは、複雑な問題を迅速かつ効果的に解決できる能力を持っており、その価値は非常に高いです。時間とともにスキルと経験が蓄積されることで、個々の専門家の市場価値が上がり、それに伴って報酬も上昇します。ベテランのプロフェッショナルは、新人や中堅社員よりも高い年収を得る傾向にあります。
業界の競争と人材獲得戦略
ゼネコン業界は競争が激しく、優秀な人材を確保するための競争も熾烈です。企業は、優秀なエンジニアやプロジェクトマネージャーを引き付け、維持するために、他社よりも魅力的な給与パッケージを提供する必要があります。特に、景気の良い時期には、多くのプロジェクトが同時に進行するため、労働市場がタイトになり、給与の上昇圧力が強まります。
インセンティブとボーナス制度
多くのゼネコン企業は、基本給与に加えて、インセンティブやボーナス制度を導入しています。これらの報酬は、プロジェクトの成功や個人のパフォーマンスに基づいて支払われます。大規模なプロジェクトが成功すると、高額のボーナスが支給されることが多く、これが年間の総収入を大きく引き上げる要因となります。
建設業界の今後の転職動向

2024年上半期には、不動産・建設業界の求人数が増加すると予測されています。これは「2024年問題」によるものです。この問題を解決するため、企業は働き方改革や現場の生産性向上を目的としたデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組んでいます。ITの導入やDXに必要な職種の求人が増えており、人材流出を防ぐために給与改定を行う企業も増加しています。少子高齢化に伴う人手不足と相まって、求人数の増加が見込まれています。
「2024年問題」とは?
「2024年問題」とは、労働基準法の改正により、長時間労働の是正を目的とした時間外労働の上限規制が2024年4月1日から建設業界全体に適用されることを指します。これにより、企業は勤怠管理の強化、残業時間の抑制、割増賃金の見直しに取り組む必要があります。従来は長時間労働で対応していた業務も、人員補充やDXによる自動化で対応する流れが強まっており、業界全体で働き方改革と生産性向上が進められています。
DXの推進と求人の拡大
建設業界では、DXの推進により、ITスキルを持つ人材やDXプロジェクトを推進できる人材の需要が急増しています。例えば、AIを用いた建設プロジェクトの管理、ドローンによる現場監視、3Dプリンティング技術の導入などが進んでいます。このような新しい技術の導入により、現場の効率化と生産性向上が期待されています。
給与改定と人材確保
人材の流出を防ぐため、企業は給与改定を積極的に行っています。賃上げを広く実施することで、優秀な人材を引き付け、維持する戦略が取られています。特に、技術職や管理職など高度なスキルが求められるポジションでは、賃金の見直しが進んでいます。これにより、建設業界は他業界と比較しても競争力のある報酬を提供できるようになっています。
少子高齢化と人員不足
少子高齢化による労働力不足は、建設業界全体に大きな影響を与えています。若年層の労働者を引き付けるための取り組みや、シニア層の再雇用など、多様な人材活用戦略が求められています。企業は、これらの人材戦略を通じて、労働力不足に対応し、持続的な成長を目指しています。
まとめ
2024年のゼネコン業界における高年収企業ランキングは、各社の競争力や成長性を反映した結果といえます。特に技術革新や海外展開を積極的に進める企業が高い給与を実現している傾向が見られます。建設業界への就職やキャリアアップを考える際には、給与だけでなく企業の将来性や働きやすさも重要なポイントです。ぜひこの記事を参考に、業界の最新動向を把握してみてください!